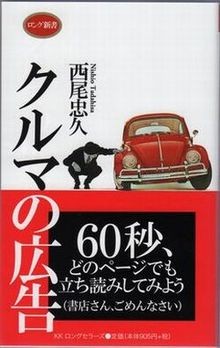ウェルズ・リッチ・グリーン社(了)
 つねづね、「広告していないものは存在していないに等しい」というものだから、自己宣伝に長(た)けているように思われてきましたが、自分自身では、はにかみ屋で、めんどうくさがり屋で、あがり屋で、口下手で、考えていることの半分も表現できていないと思ってきています。著述を出しつづけてきたのも、名刺をくばっているつもりでした。その点、メリー・ウェルズ夫人のパブリシティ上手には舌をまきつづけてきました。それだけではなく、才能豊な人たちとの交遊のひろさもうらやましく感じていました。週末にはアカプルコへ飛んでパーティ---なんてことは及びもつきません。そんな富裕なクラスとの交際をしていません。しかし、彼女は、そのパーティの常連---イタリア貴族の末裔で服飾デザイナーのエミリオ・プッチ氏と語り合い、ブラニフ航空のスチュワーデスの奇抜な制服のアイデアを伝授されています。ケタが違うんですね。もっとも、そうしたことで、パーティ費用が経費に認められたのかも。(冗談)
つねづね、「広告していないものは存在していないに等しい」というものだから、自己宣伝に長(た)けているように思われてきましたが、自分自身では、はにかみ屋で、めんどうくさがり屋で、あがり屋で、口下手で、考えていることの半分も表現できていないと思ってきています。著述を出しつづけてきたのも、名刺をくばっているつもりでした。その点、メリー・ウェルズ夫人のパブリシティ上手には舌をまきつづけてきました。それだけではなく、才能豊な人たちとの交遊のひろさもうらやましく感じていました。週末にはアカプルコへ飛んでパーティ---なんてことは及びもつきません。そんな富裕なクラスとの交際をしていません。しかし、彼女は、そのパーティの常連---イタリア貴族の末裔で服飾デザイナーのエミリオ・プッチ氏と語り合い、ブラニフ航空のスチュワーデスの奇抜な制服のアイデアを伝授されています。ケタが違うんですね。もっとも、そうしたことで、パーティ費用が経費に認められたのかも。(冗談)
気がきいていても
売らない広告は
意味がない
リッチ氏 「広告一般に関しての私の意見をお話しします。
私たちの代理店は、いわゆるクリエイティブ・エイジェンシーと呼ばれていますし、実際それはそうなんですから、そのかぎりでは喜ぶべきことですが、ほかにも、クリエイティブ・エイジェンシーと思われている代理店がたくさんあるわけなんです。そのグループの一員というふうには、私たちの代理店を思われたくないんです。
2,3年前、そうですね、アルカ・セルツァーの広告が出るころまでは、小さなクリエイティブな代理店は非常にスマートで良い広告をつくるけれども、それらは必ずしも売上げには結びつかないと思われていたんです。そこへアルカ・セルツァーの広告が出て、そういった一般の概念を打ち破ったわけなんです。
保守的な人びとの中に、『売上げと結びつかないスマートな広告には飽きた』という人が出かかっていました。
『そんな広告は、良いない広告だ』ときめつけて---まあ、広告というのは、基本的には何かを売らなければならないというビジネスですから、セリングということにいつも関心を払わなければなりません。私たちに関して、私たちが誇りうることは、私たちが気に入った作品が、同時にクライアントにも気に入り、しかもそれが売上げに結びついているということです。
秘書なんかに見せて、彼女が『すてきな広告だわ』と言ったから良い広告だと思いこんでいるたくさんの代理店のやり方に、私は、疑問を持っています。広告の良し悪しを決めるほんとうの基準は、その広告がどれだけ売上げに寄与したかということでなければならないと思います」
1時間の会談中に
3社の広告主が
コンタクトをとってきた
広告関係誌が伝えるところによると、WRG社の創業1年半日の1967年末の扱い高の合計は、4,000万ドルに達したとのことです。
4,000万ドルといえば66年末、創業7年目にして全米で第35位の広告代理店になったPKL(DDBから独立したパパート・ケーニグ・ロイス)が、ちょうど4,000万ドルですから、空前の飛躍です。
そういえば、私とリッチ氏とが話し合うている1時間ほどの間に、ウェルズ夫人が3回ほどリッチ氏に耳打ちにきました。そのたびにリッチ氏は、
リッチ氏 「chuukyuu、また新しいアカウントから照会があったよ」
ニヤリと笑ってみせました。
3回目のときなどは指を3本立て、
リッチ氏 「君と話している1時間のうちに、3つのアカウントが話を持ってきたわけだね」
と言いました。
【chuukyuu補】 40年後のいま、スクリプトをリライトしながら気がつきました。あれは、取材者に対するデモンストレーション(演技)ではなかったのか、と。
というのは、WRGは、つねにマスコミ(とりわけ広告業界紙・誌)に話題を提供し、広告主の関心を引きつけていましたからね。アドマンらしく、パブリシティ上手であったわけです。パブリシティに乗らなければ、ほとんどの人は、存在を意識しません。
その点、メリー・ウェルズの美貌はとくべつに有利でした。
しかし、すぐにこの思いつきを捨てました。WRGの記事に、取材中に広告主からのコンタクトの電話があったなんて書いた記事を読んだことがなかったことに気がついたからです。
そういう演技をすれば、どこかでボロがでて、鋭敏なジャーナリストに暴露されるはずだからです。
chuukyuu 「そんなに急激にクライアントをふやして、人材のほうは大丈夫なんですか?」
リッチ氏 「うちは初心者を入れないんでね。普通の代理店は100万ドルのアカウントにつき4人の人間を当ててるけど、うちはベテランばかりだから3人で当たるわけです。ハードワークを覚悟の上でやるんです」
chuukyuu 「ハードワークにも限界があるでしょう」
リッチ氏「うちは、スーパバイジング・システムをとってないんです。担当者が責任をもってやるシステムなんです。
担当者の自由にさせています。だからできるんです。テレビ制作部もありませんよ。コピーライターがスクリプトを書き、アートディレクターが絵をつける。それでおしまいです」
人材について、ウェルズ夫人は1967年4月17日号の『アド・エイジ』誌にこう話しています。
「私たちは必要なだけの人材を持ち合わせています。私たちのところには、約100人のスタッフがいます。また、私たちのところには、養成課程がありません」
「私たちのところには、DDBやティンカーやヤング&ルビカムやPKLなどと同じように、経験豊かなスタッフがいます。そして、現在もこれからも、彼らがいれば、クライアントが望むことをするに十分なのです」
DDB時代は終わった?
新しい代理店が
必要とされている
そんなことは、どうだって言えます。私の注意をひいたのは、ウェルズ夫人の次の言葉でした。
「代理店を辞めて自分自身の代理店をつくる人びとのうちの多くは、結局は、自分が出てきた代理店の真似をしています。
私たちはそうはしなかったし、これからも決してそうはしません。私たちの見るところ、古い代理店のサービスはもはや必要とされていません。私たちが扱っているぐらいの大きさの広告主の大部は、自分たち自身のマーケットとリサーチ・サービスをもっていて、かつては代理店が準備していたあらゆる機能を扱っています」
すると、WRG社は、DDBにもジャック・ティンカー&パートナーズにも似ていないとウェルズ夫人は言うのでしょうか? 確かに、ウェルズ夫人は、あるところで「DDBの時代は終わった」と公言しています。
DDBのように、良い製品だけを扱っていれば失敗はないというのです。それにひきかえ、WRGが扱いたいのは、普通の製品である。それをアイデアの息吹きをふきかけて売ってみせるというのです。
しかし、 リッチ氏はそうは言いませんでした。
chuukyuu 「DDBをどう思いますか?」
リッチ氏 「まじめで、誠実で、クライアントに問題があれば引き受けませんね」
chuukyuu「PKLは?」
リッチ氏 「技巧的で、ニヤッと笑って人を斬る、ってところがありますね」
chuukyuu「WRGは、どっちです?」
リッチ氏 「DDBのほうをとりますね」
とDDBを気にしているような発言をしています。 ウェルズ夫人は副社長としてDDBに勤め、リッチ氏は単なる1コピーライターとしてDDBで働き、そのあと「なぜオレはDDBを辞めたんだろう」と考え続けたといいますから、DDBについての発言が違っても仕方がないのかもしれません。
しかし、WRGの行き方は、私の見るところでは、DDBとたいして変わっているようには思えません。
ただ、ブラ二フ航空の成功のために、クライアント側は、ウエスタン・ユニオンの例のように、彼らがブラニフに提供したマーケティング活動を助けるような新しいサービスの提案を期待していますが---。
ウェルズ夫人がフィリピンのマルコス大統領の歓迎パーティに招かれ、ホワイト・ハウスに一晩とどまり、ジョンソン大統領と何ごとかを話し合ったことから、次期大統領選挙キャンペーンを担当するのではないか---との噂がもっぱらだったこともあり、とにかく、この代理店は話題の多い会社です。彼女自身はそれを 「もし大統領に頼まれれば、いかなる援助も惜しまないつもりですが---」との但し書きをつけて否定Lはしましたが。
【老婦人】
ブラニフ航空の機内---老婦人と隣席に中年男性。
サイケ模様のダービー帽とストッキングのスチュワーデスがキャンディをくばる。
1ヶとってとりあうず座席の肘置きにのせる男性。
老婦人のほうは、トレイいっぱいのキャンディを膝の手提げ袋へ全部落しこむ。
びっくりした表情で、あわてて肘置きのキャンディを取る男性に、にっこりと無邪気な顔を向ける老婦人---この、一見、上品そうな老婦人の選定がうまいから、いやらしさが消されている(ただし、この年代の一部の婦人の傍若無人ぶりは万国共通らしい。老婦人が、あと、何を記念品としてしまいこんだかは、映像で)。
終着空港に到着。降りる乗客たちをやりすごした老婦人は、やおら、上の収納棚から毛布を肩へ。
タラップでは、スチュワーデスが老婦人の荷物に驚くが、「お手伝いいたしましょうか?」
その映像にかぶせて、アナウンス。
「私どもブラニフ・インターナショナル航空は、去年、空の旅を一新いたしました。
みなさんのお気に入っていただけるかどうか心配でしたが---どうやらおに召していただいた方がすこし多すぎるみたいです。
もちろん、私どもは、搭乗記念品あさりに反対はいたしません」
世界遺産に指定されたマチュ・ピッチュを売ったブラニフ航空の広告
マチュ・ピッチュの呪い
マチュピチュでは、あなたは招かれざる客です。
インカ族が、未婚女性のかくれ家としてこの町をつくりました。 (これは、原始的なプレイボーイ・クラブのようなものです)。しかも訪問客を寄せつけないように、未知の世界のまっただ中につくったのです。
7,120フィート登ったところに、呪いがあるのです。まず、ジェット機(できれば当社の)でペルーのリマへ飛び、乗り換えてクスコへ。ここで汽車に乗り、ガタゴトゆられて幾つもの山を越え、廃墟のふもとにたどりつきます。
こんどはバス。デコボコ道を走るとホテル。
そこから残る数千フィートは歩いて登ります。頂上まで。
ここは、息もつけないほどの場所です。ここは世の中で最も壮観な場所の一つなのです。しかも魅惑的な---。
これで、なぜ、たくさんの人びとがここにくるかがおわかりになったでしょう。呪いがあるにもかかわらず。
【chuukyuuアナウンス】
いま、書店の新書版コーナーに西尾忠久の新編著『クルマの広告』が積まれているはずです。立ち読み---というか、立ちめくりをしてみてください。
ご感想をこちら↓のコメント欄へ、ぜひ。